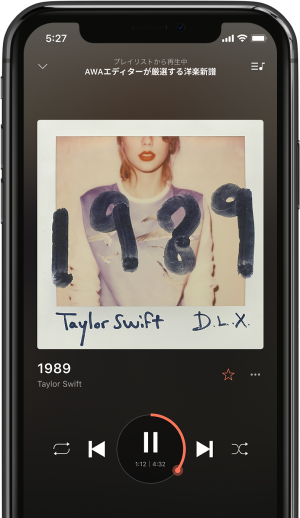説明文
親父の思い出としてとても印象の強い
映画 007シリーズ。
とにかく親父はショーン・コネリーが大好きで、
「男の中の男だ」なんて、本人を知っているわけでもないのに、
映画の中の彼だけを見て、本気でそう言っていたように思います。
ボンドがロジャー・ムーアに変わってからも、
「やっぱりコネリーじゃなきゃダメだ」なんて言いながらも新作を楽しみにしていました。
テレビの再放送や、映画館で親父と二人で観た
007シリーズ。
親父が亡くなってもう三十年以上も経つのに、
こんな曲たちを聴くと、彼の下手な映画解説の声が聞こえてくる気がしてしまいます。
007シリーズ前期(1950~1980)AI解説
1. 原作の誕生と冷戦下のリアリズム(1950年代)
映画シリーズが始まる前、小説はすでに東西冷戦下の緊張感を背景に描かれていました。
* 敵対組織: 初期原作の主な敵は、ソ連の秘密組織**「スメルシュ (SMERSH)」**でした。これは「スパイに死を」を意味し、冷戦の脅威を象徴する存在として描かれました。
* ボンド像: 原作のジェームズ・ボンドは、ショーン・コネリーが演じたような洒脱な遊び人というよりは、**「冷酷で孤独な●人許可証を持つ男」**という側面が強調されています。英国が国力を失いつつある中で、国際社会での存在感を示すための孤独な戦いがテーマの一つでした。
2. 初代ボンド:ショーン・コネリー期(1962年~1971年)
コネリーがボンドを演じたことで、シリーズのイメージは原作から大きく飛躍し、世界的な大ヒット作となりました。
* 映画のスタイル: 原作のハードボイルドさに、エキゾチックなロケーション、派手なアクション、ユーモア、そして最先端のガジェットが加わり、「スパイアクション映画」のフォーマットを確立しました。
* 敵対組織の変更: 冷戦の影が薄れる中、原作のスメルシュに代わり、映画では国際犯罪組織**「スペクター(SPECTRE)」**が主な敵として登場します。これにより、シリーズはよりフィクション性の高いエンターテイメント路線へとシフトしました。
* 代表作: 『007 ドクター・ノオ』、『007 ゴールドフィンガー』など。
3. 短命なボンド:ジョージ・レーゼンビー期(1969年)
* 原作への回帰: 映画**『女王陛下の007』**は、原作小説の中でも特にボンドの私生活と感情が深く描かれたシリアスな作品をベースにしています。
* 人間味のあるボンド: レーゼンビーは、コネリーとは異なる、不器用で、真実の愛を求める人間味あふれるボンド像を表現しました。この作品でボンドは結婚し、そして妻を失うという、シリーズで最もドラマチックな展開を迎えます。
4. ユーモアの時代:ロジャー・ムーア期(1973年~1985年)
ムーアのボンドは、ベトナム戦争後の**デタント(緊張緩和)**や、1970年代の社会のムードを反映し、シリーズを大きく方向転換させました。
* 映画のスタイル: ユーモア、コミカルなアクション、壮大なSF的設定(宇宙や巨大な海底基地など)、そしてロマンティックな要素が強調されました。ボンドは「冷酷なスパイ」から、**「魅力的なプレイボーイで洒落の効いたヒーロー」**へと変化しました。
* 現実逃避的エンタメ: この時期の作品は、現実の政治情勢から離れ、純粋なエンターテイメントとしての要素を追求しました。
* 代表作: 『007 死ぬのは奴らだ』、『007 私を愛したスパイ』など。
5. ハードな回帰:ティモシー・ダルトン期(1987年~1989年)
ムーア期の後に登場したダルトンは、シリーズを再び原作の路線に近づけようと試みました。
* 原作重視: ボンドを原作に近いシリアスでタフなスパイとして再定義。ユーモアは控えめになり、冷酷さや怒りを露わにする場面が増えました。
* ハードボイルド路線: 特に**『007/消されたライセンス』では、ボンドが私的な復讐のためにMI6を離脱し、麻薬カルテルと戦うという、当時としては異例のハードでパーソナルなストーリー**が展開されました。これは、後にダニエル・クレイグ期で主流となるシリアス路線の先駆けとも言えます。
このように、1980年代までの前期は、原作のハードボイルドから始まり、ショーン・コネリー期で大衆娯楽の頂点に立ち、ロジャー・ムーア期でコミカルなSF路線を経て、ティモシー・ダルトン期で再び原作のリアリティへの回帰を試みる、シリーズの方向性を探る時代でした。
…もっと見る